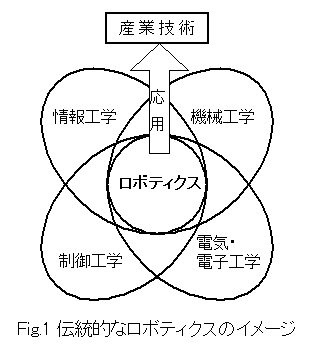
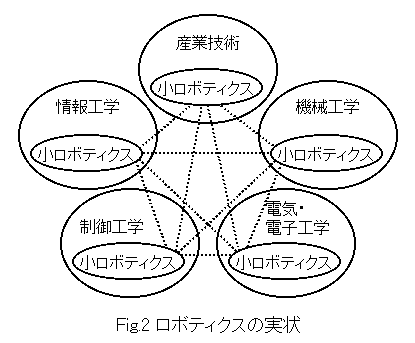
筆者は第18回日本ロボット学会学術講演会(RSJ2000)において,豊田工業大学の梅谷陽二氏とともに「ロボティクス史・ロボティクス論」と題したオーガナイズドセッションを企画した [1]-[10] .また,同講演会の特別行事においては,梅谷氏による「ロボット工学概論はあるか?」,立命館大学 兵藤友博氏による「科学史・技術史から見たロボティクス」と題した特別講演とともに,「ミレニアム討論会」が開催された [11] .これらは,深刻化する産業界と学界の乖離や,ロボット研究を取り巻く社会的な環境の大きな変動の中で,見失われがちなロボティクスの全体像を科学史・科学論の観点から再検討する,という試みであった.
本稿では同OSおよび討論会において示された論点を紹介するとともに,筆者自身の解釈を加えたい.またRSJ2000において筆者が提唱した「ロボティクス論」という観点についてさらに詳しく述べ,実践におけるロボティクス論という立場から,現在のロボット研究が持つ構造について一つの考察を試みる.
2.RSJ2000における論点まず,RSJ2000のOSにおける講演および討論会における発言をいくつかに分類し,その要約を以下にまとめよう.
(ロボティクスの定義と方向)
(ロボティクスと産業)
「ロボティクスは対応する産業がないため工学ではなく,学問体系と方法論がないため科学でもない.人々の感性に訴える芸能の世界である.ロボット研究の成果が利用されないのは体系化が不十分であり,コスト意識が希薄だからである.一つの方向としてサイバービジネスへの進出がある.[11](豊田工大・梅谷)」
「知能ロボットを実用化するには,まず製品化して実際に使用し,それについての理論的考察に基づいて改良しつつ普及する,というサイクルに乗せる必要がある.実用化を意識したコスト・パフォーマンスの高い研究が必要であり,コストや安全性,信頼性の向上も研究ターゲットとすべきである.[6](東北大・中野)」
「ロボット研究においては真理の探究を目指す純粋科学的な研究課題と具体的効用を求める技術開発とを峻別する必要がある.また研究を実用的成果に結びつけるには,画一的な有用性のイメージにとらわれず,研究課題を取り上げた動機から離れて適切な応用分野を発掘する努力が必要である.[7](機技研・谷江)」
「単純で過酷な労働から人間を解放することにロボットへの期待があり,そういうロボットの実用化にロボティクスの社会への貢献がある.[11](HEW・小坂)」
「生産システムや危険作業においてロボットは既に色々な用途に使われ,役に立っているが,その基本となっている技術はティーチングプレイバックである.80年代以降のロボット研究で具体的なものが何か出てきているかは検討の必要がある.[11](立命館大・渡部)」
「ロボティクスにおいては産業界の物作りの立場とサイエンスである大学の立場の分担がうまく機能していないため,それらの間でギャップが生じ閉塞状況にある.学会はそういう分担を整理して発信すべきである.[11](日立・藤江)」
「現在のロボティクスはロボットの定義が狭くなっており人間の機能に閉じこもっている.ヒューマノイドや自律性にこだわらず,人間を超えた機能を目指すことで,ロボット工学の応用がさらに開ける可能性がある.[11](日立・江尻)」
(ロボティクスと社会)
「ロボット技術は人間の労働を代替するという動機から発しており,人間の想像力を越えた夢の実現と言うよりは現実の課題を地道に解決する目的指向で問題解決型の技術である.そのため技術が社会に与える影響の評価が容易であり,現代の科学技術社会における技術のあり方として重要な意義をもつ.[5](筑波大・油田)」
(その他)
「各研究者が自分の研究をどう評価しているかが重要である.[11](東大・稲葉)」
「ロボティクスは教育の手段として有効である.[11](名大・生田)」
このように問題は多岐にわたっているが,ここでは一つ一つの意見についての詳細な論評は行わない(むしろそれは各読者にお任せしたい).これら全体を眺め渡したとき,まず感じるのは(半ば予想通りではあるが)「ロボティクス」という言葉の定義すら各自まちまちだということである.また,どの分野の研究者もほぼ例外なく「自分の研究は重要であるにもかかわらず現在のロボティクスの中では周縁的な一分野であり,今後はより力を入れるべきである」と考えているという印象を受ける.こうした感じ方が研究者の間に広がる閉塞感の一因になっているとも言える.
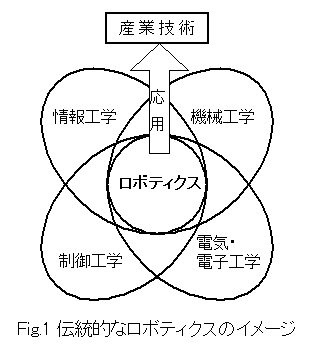
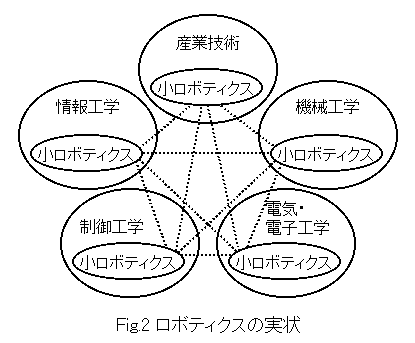
我々が抱いてきた伝統的なロボティクス観はFig.1のようなものではなかったか.情報工学,機械工学,制御工学,電気電子工学など多くの分野の境際融合領域としてロボティクスという一つの学問分野があり,その研究成果が産業技術として応用される,という図式である.現在はそうなっていなくても,少なくともそれを目指している,というイメージを持っていたと思う.
しかし,上のような事情を考えると,こうしたイメージはロボティクスの実状および進みつつある方向を正しく反映していないように思われる.それはむしろFig.2のように表されるのではないか.つまり,各分野の中にそれぞれロボティクスに属するとされる分野の島(「小ロボティクス」と呼ぼう)がある.各分野内では小ロボティクスとそれ以外の分野の境界は比較的明瞭であり,小ロボティクスはそれぞれに体系化が進んでいる(そのことが研究者にロボティクスという体系化された一つの学問分野の存在を錯覚させる).こうした小ロボティクスが緩いネットワークで結ばれてロボティクス全体を形成している.「ロボティクス・コア」は存在しないのである.
ところが,小ロボティクスはそれぞれ異なるパラダイムを持つ分野の中にあるため,それらの間には科学論で言う共約不可能性 incommensurability が存在する.これがロボティクスの定義の違いを生み,ロボティクスが全体として体系を持たないという批判 [2] につながる.また,ある小ロボティクスが大きく変化したり,新たな小ロボティクスが生まれても,他の小ロボティクスは直接影響を受けない.産業界におけるロボット研究もまた,これらの成果の受け皿ではなく,独立した小ロボティクスを作っている.産業界と学界の連携がうまく機能しない原因の一つは,この構造にあるだろう.
さて,このようなロボティクスの形態は,もともと異分野の研究者が結集してロボティクスのコミュニティを作ったという,歴史的な経緯により形成されたものである.これは一つの学問が様々な分野に専門分化するという通常の道筋とは異なっており(小ロボティクスの内部ではそれが起きているが),学問分野として不安定な感じを与える.学問の流れをさかのぼっても接点が見出せない,無矛盾の体系が構築できないのである.
この不安感が,体系化の願望 [2] やシンセシス,システム・インテグレーションの夢 [4],[8] へと研究者を向かわせているように思う.Fig.1のイメージへの回帰である.しかし,統合は応用の文脈からの要請があって,初めて効果を生むものであろう.またそれは永続的な学問分野(discipline)よりも一時的かつ transdisciplinary な研究体制になじむものであることが指摘されている [12] .そうしたタイプの知的生産は,例えば外科手術ロボットの開発プロジェクトなどに見られる.
今後のロボティクスの方向について,筆者に明確なビジョンがあるわけではない.ただ,ロボティクスの学問としての構造と特性を実態に即して把握すること,それを利用して何ができるかを検討することが第一歩ではないかと考えている.Fig.2→Fig.1が唯一の解とは限らないとも思われる.
3.ロボティクス論の視点筆者はRSJ2000において,主にロボット技術の内容について考える「ロボット論」に対置して,ロボティクスという学問自体のあり方を論じる「ロボティクス論」という視点を提唱した [1] .RSJ2000では筆者自身はもっぱら聞き役に回って,こうした視点にこだわらず自由な議論を引き出すことに努めたため,その考え方はあまり浸透したとは思われない.実際,前章に示した論点の多くはむしろ「ロボット論」に属するものである.そこで本稿では改めてこの視点を強調し,それに基づいた考察を試みたい.
「ロボット論」ではロボットという研究対象,すなわち何を研究するかを扱うのに対し,「ロボティクス論」ではそれを研究する上での枠組みや研究者の立場,なぜ,いかに研究するかということを扱う.つまり「ロボティクス論」では研究者の側の人間的な要素を重視する.端的に言えば「こういうロボットを研究したい」というのが「ロボット論」であり,「ロボティクス論」では「『こういうロボットを研究したい』と考える研究者はいかに形成されたか」までを考える.
言い方を変えれば,「ロボティクス論」とは,ロボティクスを,研究者の集団とその組織から構成される一つの「システム」とみなして,その現状と成り立ちを再点検しよう,という立場である.従来のロボット論の考察の範囲は,研究対象であるロボットだけを切り離し,ユーザとしての社会までを含める程度だった.一方,ロボティクス論では,特に研究者集団についての自己言及的な論考に重点を置きつつ,研究者集団・研究対象・一般社会の相互関係をも包括的に考える(Fig.3).
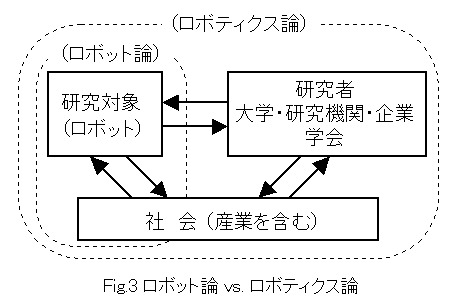
ロボット研究者の集団はそれ自体が一つの社会を形成している.その研究活動の拠点となる学会が実体として組織され,学術誌や学術集会を持っている点で,その社会は十分に制度化が進んでいると言える.そこでまずその集団内部における行動様式が,社会学的あるいは文化人類学的な分析の対象になる.また,その社会が持つ構造の形成過程については,歴史的な観点からの考察が必要である.さらに,研究者集団の外部に対する社会的機能を論じる際には,ロボティクスにおいて産業と学問は必ずしも一枚岩とは言えないから,むしろ産業界を含む一般社会と研究者集団との関わり,という形で考えねばならない.
こうした視点をとることが必要であると考える理由は,以下のようなものである.比喩としてロボティクスをFig.4のような一つの動的システムと考えてみよう (文献 [14] では科学・技術を進化システムとみなして考察を行っており,この観点も興味深い).ここでロボティクスにおける研究内容の総体は,システムの状態変数と考えることができる.この状態変数に対して,ある関数により出力が決定される.これが研究成果である.出力に応じて何らかのフィードバックによりシステムへの入力が与えられる.入力とはすなわち研究予算,人材,設備などの研究資源の投入である.そして現在までの研究内容や研究資源により研究内容は変化していく.
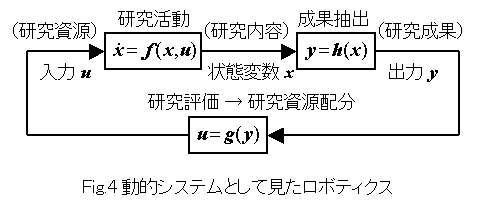
ここで注意すべきことは,状態変数=研究内容や出力=研究成果は,ロボティクスというシステムの構造に強く依存するということである.システムは無制限に任意の状態や出力をとりうるわけではない.素朴な「ロボット論」は,システムの構造を考慮せずに状態変数や出力あるいはそれらの目標値のみを論じるに等しい.「良い制御」を行うためには制御対象のモデリングが必要なことは制御理論の常識である.「ロボティクス論」とは,いわばロボティクスというシステムのモデリングを行うことにより,それが到達しうる研究成果の限界を見極め,さらには「より良い」システムとはどういうものかを考える,という試みである.
また,研究者の自由意志と責任という問題について考えてみよう.ロボティクスにおける学界と産業界の乖離や学問としての閉塞状況などの問題について,それらを個々の研究者の「心懸け」に帰する意見が多く見られる.もちろん,研究活動の実践を通じてそれらを解決する(あるいはしない)という判断について,最終的に責任を負うのは研究者個人である.しかしながら,そういった問題が生ずる傾向が,現時点でのロボティクスというシステムに構造的に内在するとすれば(筆者自身はそう疑っているのだが),その根本的な解決は,システムの中に束縛されている一人一人の研究者の手には余ると言わざるを得ない.解決の糸口は,ロボティクスの実態をできるだけ忠実に反映したシステムのモデルについての認識を,多くの研究者が共有するということにあるだろう.
むろん上に述べた動的システムというのは一種のメタファーにすぎない.現実のロボティクスの姿はもっと複雑なものであろうし,数理的な手法によるモデリングが可能とも思われない.ロボティクスの実態に即した構造を,人間的な要素を重視しつつ記述するには,むしろ人文科学・社会科学の分野の手法を取り入れることがより有効だろう.特に,こうした問題を一般の科学に関して考察する学問として,科学史・科学論(科学哲学・科学社会学)という分野がある [13] .実はロボティクス論というのはこれらの観点を援用しつつロボティクスという科学の一分野について考えよう,ということでもある.
さて,このような観点に立てば,ロボティクスの技術内容や知識体系の総体が決して客観的な,フラットなものではなく,研究者社会の構造に起因する有形無形の制約によってバイアスがかかっていると疑うのはごく自然なことである.個別の研究課題の選択といった基本的な問題についても,それが白紙の状態から行われることはまれであって,研究者や指導者の学問的バックグラウンド,研究者が所属する組織の性格,利用できる研究資源の範囲,許される研究期間,研究業績の上げやすさなどの人間的な都合に左右される.技術的要請に迫られて研究に着手するのではなく,最終的目標が遙かに遠くかつ曖昧に設定されており,あまつさえそれには到達し得ないことを自ら宣言することさえあるロボティクスにおいては,課題選択における恣意性が高く,したがってこれらの事情が優先される可能性もなおさら大きい.一例として,ロボット用のアクチュエータやバッテリーの研究が,必要と言われつつもあまり行われない理由は,こうしたところにもあると考えられる.
また,研究者と一般社会との関わりにおいて,もう一つ考慮すべき問題がある.研究者も人間である以上,我々が所属する一般社会や文化に固有の先入観や偏見に否応なく染められている.そのことが,研究者の主観やイデオロギーに強く依存すると思われる分野,例えば知能や福祉といった微妙な問題を扱う分野における技術内容や知識体系に影響を与える要因となる恐れもある.科学社会学においては技術や知識についてのこうした捉え方を社会構成主義 social constructivism と呼び,詳細な検討を行っている.
4.実践におけるロボティクス論 - Robotics in action -RSJ2000のOSおよび討論会においては,主にロボティクスのあるべき姿や進むべき方向についての議論に焦点が置かれていた.ロボティクスの学問としての理念に関するこのような議論が非常に重要な意義を持つことは言うまでもない.しかし一方で,ロボティクスの現在の姿を眺めたとき,そうした理念とは無縁な要素によって研究の方向が決定されることも多いという事実から目をそむけることはできない.これらの要素を無視した記述では,ロボティクスというシステムの正確なモデリングは望むべくもない.理念としてのロボティクス論と並行して,現実に進行する研究活動の実態を冷徹に見据える,実践におけるロボティクス論が必要な所以である.
科学論の分野において,クーンによる有名なパラダイム論などに端を発して,科学を研究者の理念的な倫理規範や知識・認識形態の観点からとらえるのではなく,実践の観点からとらえる science in action という立場がある.研究活動の現場の文化人類学的研究である実験室研究や,前章でふれた社会構成主義はこうした流れに含まれる (これらから発した過激な科学批判について科学者からの厳しい反論があり,論争となっている [15]) .上に述べた,実践におけるロボティクス論はこれらの考え方の影響を受けたものである.
以下では,この観点に基づいて,ロボティクスの「面白さ」と論文システムの関係,それが有する問題点について一つの考察を試みる.
4.1 ロボティクスの「面白さ」について産業界における応用が低調であると言われながらも,アカデミックなロボット研究は近年ますます盛んであり,多すぎる程の講演会や国際会議が開かれ,無数の研究が発表されている.ロボティクスがこれほどまでに多くの研究者を引きつけるのはなぜか,という問いに対しては,「役に立つから」とか,「儲かるから」ではなくて,「面白いから」という答えが返ってくる場合の方が多いであろう.筆者自身,自分の研究が役に立つかと問われて答えに窮することはあっても,自分の研究を「面白い」と思う気持ちは止められないのである.
それでは研究が「面白い」というのは一体どういうことなのか.「面白い」というのはロボット研究者の世界では研究に対する最大の賛辞と言っても良いのだが,そこがまた曲者でもあって,その正体を冷静に分析する必要があると思われる.ロボティクスの「面白さ」は,ロボティクスの強みであると同時に,諸刃の剣となっている面もあるようである.面白いけれど役に立たない研究,逆に役に立つけれど面白くない研究というのがあるのは確かである.この面白さあるいは面白くなさという心理について十分に見極めなければ,役に立つ研究をやりましょうと言ってもかけ声だけに終わる危険性もある.
そこで筆者はRSJ2000において,ロボティクスの魅力は何か,ロボティクスが面白いのはなぜか,という問いを投げかけてみた.その答えとしては様々だが,
・ SF的な夢を感じるから [2], [8]
・ ロボットは感情移入型機械だから [4]
・ 機械いじり,もの作りが好きだから [8]
・ 生物(人間)の機能への挑戦だから [6]
などが見られた.これらがロボティクスに新たに参入する,特に学生諸君にとって大きな動機となることは間違いない.また現在ロボティクスに従事する研究者の多くにとっても,こうしたことによる「面白さ」が研究を支える個人的動機としてはたらいていることは確かであろう.しかし一方で,学問としてのロボティクスを維持・推進する要因として,明らかにこれらと一線を画するレベルでの「面白さ」が作用しているようにも感じるのである.
それはひとことで言えば,訓練によって獲得される職業的・専門的な「面白さ」の感覚である.研究の経験により養われた一種の審美眼,鑑賞眼と言っても良い.研究者が(自分の研究を含めて)ある研究を面白い,興味深い,と感じるときには,こうした種類の面白さを指すと考えて良いであろう.しかも,それは学術的な価値の評価とほぼ直結している.
ロボティクスにおいては,新たな真理の発見とか達成した数量的な性能を学問への貢献の尺度とすることが難しく,新規なコンセプトの提案をもって学術的貢献とすることが多い.それが価値を持つかどうかの明示的な基準を立てることはほぼ不可能で,結局は近接した専門分野(第2章の「小ロボティクス」)の研究者が興味深く思うかどうか,ということに頼らざるを得ない.このような判断を行うためには,その専門分野に精通し,現在までに何がなされているか,新たに何をなすべきか,といったことを熟知している必要がある.
しかしそればかりではなく,研究者はこうした判断の際に,ある種の経験的な直観 − ポラニーの言う暗黙知に属するもの [16] − を働かせている.それが感覚的なフィルターを通した判断であるからこそ,研究者は「この研究は優れている」というよりも「この研究は面白い」という言い方を好むのである.かといって,それは必ずしも恣意的で主観的な,各自まちまちの評価とはならない.美術や文学における鑑賞眼と同様に,各研究者で判断が完全に一致するということはないにせよ,分野の近い研究者の間ではかなりの程度で共通した評価が下される場合が多い(また制度上もそうなることが期待されている).
一方で研究を行う側に立ってみれば,やはり同様の基準で自らの研究を律するわけである.自分を含むその専門分野の研究者が共通して面白いと思う方向に研究を進める傾向がある.その結果として,ここで言う「面白さ」は,夢を感じるからといったような,一般の人が抱くロボットの面白さの感覚とはかなりかけ離れたものになっていく.個々の研究に立ち入って,その面白さを一般の人に,あるいは異なる専門分野の研究者にすら,わかりやすく説明することが困難な理由はここにあると言える.
4.2 論文システムと研究者現在,科学のどの分野においても,論文は,新たに得られた学術的知見を流通し普及するためのメディアという元来の機能をはるかに超えた役割を背負わされている [13] .ここでいう論文とは,ピア・レビューの制度を備えた学術誌あるいは一部の国際会議における論文のことである.ここではそうした論文にまつわる諸々の事象を便宜上「論文システム」と呼ぼう.論文システムが研究を動機づける上で公正かつ有効な手段であることは疑いないとしても,それに対して過度に依存した研究評価には少なからず問題があると思われる.
"Publish or perish" という言葉が示す通り,論文システムは研究者の生殺与奪を握っていると言っても過言ではない.大学・研究機関においては,新たに採用する研究者を公募することが一般化しており,必ず学位と研究業績,具体的には最近何年間かに発表した論文数が応募条件に含まれる.任期付き研究者制度や各種のポスドク制度などにより研究者の流動性が高まるにつれ,次の就職先を見つけたりパーマネントの地位を得るためには,短期間で着実に論文数を上げることが特に若手研究者に要求される.また大学・研究機関の組織内での昇格・昇級においても,最近の論文数が最も重要な評価基準とされる.また教育の場においても,大学院制度の重点化により学位取得者が増加するにつれ,そのために必要となる論文も増えている.さらには,政府などが公募する研究プロジェクトの提案においても,参加研究者の業績リスト提出が義務づけられ,それが研究能力の審査対象となることも少なくない.また,論文の数ばかりではなく質も格付けされる傾向にあり,発表誌のインパクト・ファクターや論文の被引用度も評価の対象にされつつある.
以上のように,査読付き論文を発表することへの各種のインセンティブが設定される一方,論文を書かなければ研究生活・実生活ともに支障をきたす事態を招くような状況が動かしがたいからには,研究者はほとんど偏執的に論文を書き続けざるを得ない.ロボティクスにおいて多くの研究発表が行われているのも,実はそれを聴く側ではなく発表する側に需要があるからである.その結果,論文システムは研究の付随物というよりも,その中心の位置を占めるようになる.研究を行った成果を論文にまとめるのではなく,効率的に論文を書くために研究を行うということが生じる.これは目的の転倒として非難して言っているのではない.論文が研究の副産物ではなく最終生産物として制度上は位置づけられている以上,それをできるだけ効率良く生産できるように研究課題の選択や研究資源の配分を最適化することは,きわめて合理的な行動と言える.
(企業における研究も,研究を行った結果を商品にするのではなく,効率的に利潤を追求するために研究を行うのであって,目的の違いはあっても基本的な論理は相似である.)
さて,4.1節で述べたような,研究に対する職業的な「面白さ」の感覚は,論文システムと密接な関係がある.言うまでもなく,論文の査読者はこうした鑑賞眼を最大限に働かせて,論文の評価を行う.明らかに間違った内容の論文を除いては,論文の採否を機械的に決定する基準はない.学術誌ごとに査読基準や採点システムを工夫していても,最終的な判断においてそれらに注意が払われることはむしろ少なく,査読者は自らの鑑賞眼を信用する場合が多い.複数の査読者の判定が食い違うことはあるとしても,それは査読の制度を無意味にするような程度ではなく,おおむね判定は収斂する.肯定的な評価は,ほとんど必ず「興味深い」という表現を伴う.かくして,同業者の「面白さ」の感覚に適合した論文のみが,学術的な貢献の認定を受け,世に送り出されるのである.
一方,こうした鑑賞眼の養成においても,論文システムは重要な役割を果たしている.研究者はそのキャリアの初期において,研究に取り組む分野における大量の論文を読む.それはその分野における基本的な知見を学ぶということの他に,その分野において興味深いと認められている研究のあり方を学ぶという意味も持つ.その分野で既に何が達成されているか,どんな方法論が使われているか,といった知識だけでなく,その分野で面白いとされる研究のスタイルが無意識のうちに刷り込まれる.論文にはそれぞれの専門分野に応じてある種のパターンがある.これは,ロボティクスに関する論文と,例えば材料科学や生物学など異なる分野の論文を比較すれば歴然としている.これは研究スタイルの反映であると同時に,逆にこうしたパターンが研究スタイルを規定しているとも言える.
また,「面白い」研究のスタイルを未だ確立していない研究者,例えば学生が書いた論文の初稿を読むとき,その指導者は自らの美意識に著しく反するものを見出す.基本的な表現力の欠如といった問題は別として,書くべきことが書かれず,書かなくても良いことが書いてある.守るべきと思われる論文の定石から大きく外れているのである.研究者の卵は指導者による添削を繰り返し受け,またこれまでに読んだ論文が共通して持つ型を真似て論文を書くうちに,こうしたパターンを身につけてゆく.それは論文を書く際に必要かどうかという観点でデータを取捨選択し,必要なデータだけを効率良く得るために研究の計画を立てるようになることも意味する.
さらに進んだ段階の研究者においては,研究室内のディスカッションなどで研究の進め方や新たなアイデアの提案を行うことがある.そのときそれを採用するかどうかの最も重要な基準となるのが「論文になる」ということであり,ここでもやはり「面白い」という表現が使われる.また実際に論文を投稿し査読を受けることを通じて,身につけた「面白さ」の感覚はテストされ,強化あるいは修正される.こうした過程はスポーツやゲームにプレイヤーが熟達する過程とも類似したものである.
以上のようなことを論文システムを軸として繰り返すうちに,研究者は研究に対する職業的な鑑賞眼を獲得するに至る.このとき研究者は自分の感じる研究の「面白さ」と学術的な価値が同一のものであると信ずるようになる.また自分自身の研究を面白いと感じているからこそ本気で打ち込むのである.一方,その感覚的な規範から外れた研究は自己抑制される.この段階に到達した研究者が今度は論文の査読者として機能するのである.
このように,職業的・専門的な「面白さ」の感覚の,論文システムを媒体とした再生産プロセスは,全体としてポジティブ・フィードバックの様相を呈する.それに適合した研究のスタイルはより強固になり,研究者の間で増殖していく.また(組織の性格にもよるが)「論文になる」研究には研究資源も優先的に配分される場合が多い.
さて,ロボティクスにおける産業界と学界の乖離について,産業界からの批判があり,また学界からの反省もある [2], [6], [11] .その原因について学界の論文重視ということも指摘されている.ここまでの分析から言えることは,産業界に役に立つ研究は一般に「面白くない」,すなわち論文システムと「面白さ」がエンカレッジする研究の拡大再生産の過程から外れている,ということである.ロボティクス以外の産学の協力がうまく機能している工学分野では,おそらくそのループが産業界の要請と良く一致しているのだろう.
ただ注意せねばならないことは,産業界と学界は同じくロボット研究を行っているように見えて,実は全く異なったルールのゲームを進めている,ということである.論文システムのゲームは学界全体に制度の上で根深く浸透しているばかりでなく,研究者のエトスにも大きく影響を与えている.その認識なくしていたずらに産学連携を叫び,研究方向の修正を主張することはすれ違いしか生まないであろう.
ここでもやはり具体的な処方箋を示すことはできないが,上に述べたような構造の存在を各研究者が認識することが出発点となるだろう.「ゲームのルール」を十分把握した上でそれを利用し,可能な範囲で修正することも視野に入れるべきだと思われる.ルールは自然発生的に形成されたものとは言え,それはやはり人間の営みから生まれたものなのである.
5.おわりに学問としてのロボティクスを考える上で,実践におけるロボティクス論という立場を主張し,その具体例として,ロボティクスの「面白さ」と論文システムのある側面について考察を試みた.本稿における分析は主に筆者自身の研究者(論文執筆者,査読者,編集者,研究指導者)としての経験と自己観察に基づく.筆者自身の主観的な解釈であり,もとより一般性のある議論とはなっていないが,こうした一つの視点がロボティクスというシステムの「モデリング」に資するところがあれば幸いである.
参考文献