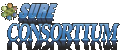第43回
バルク選別の不確実性 ③
~どう自動制御するか~
どう自動制御するか
前回の「不確実性の改善余地」では、現状、改善し得る策は限られていることを述べた。試行錯誤の結果として分離効率が改善される余地はあるが、選別対象物が変わればその効果は維持できない可能性が高く、また、選別結果を計算で予測したり、それに基づいて最適条件に自動制御することは難しい。筆者は現在、選別装置やこれを複数組み合わせた選別システムに対して、不確定要素をできる限り数学的に処理し、自動制御するための筋道を整理している。具体的には、第33回で述べた電子素子選別に対するAESSを拡張して一般化し、多くの素材・選別装置で対応できる計算システムを検討中である。今回は、筆者の現在の研究開発をベースに、バルク選別装置自動制御の可能性について展望してみる。
ここでいう「不確実性」とは、現時点では定量的な把握ができないため、この不確定要素によって、どのような分離効率の低下が起きるか予測できないということである。予期し得ない偶発的・突発的な要因ではなく、そこには必ず秩序が存在する。未来において、これらを精度よく把握する技術が開発されれば、その要因が解消できるかはともかく、少なくとも不確実な事象ではなくなる。不確定要素を、最適選別条件を算出する計算に少しでも取り込むことができれば、人の経験に依存しない安定した自動制御によって、第40回・図6.1.1の「実現可能な最大分離効率」を向上させることが期待できる。このような思想に基づいた筆者らの現状の研究開発の展望を、ごく簡単に整理すると以下のようになる。
「単体分離」の把握については、筆者らは現在、粗粒の人工物に対する単体分離分析技術を開発中であり、近い将来、分析できるようになる予定である。また、計算によって破砕工程を最適化することはできないが、自動解体工程を開発し、明らかに破砕特性の異なる部品を事前に切り分けたり、その後、各破砕特性を持つ部品に適した破砕機の選択を以て、良好な単体分離を達成するシステムを検討中である。「ヘテロ凝集」は、特に細粒に対する湿式選別で影響してくるが、残念ながら、現時点で抜本的な解決の見通しは立っていない。当面は「ヘテロ凝集」しにくい、mmサイズ以上の粒子を対象とする乾式選別装置を優先して、自動制御化を進める予定である。「場のムラ」については、過去に筆者が開発した選別装置では既に解消できているものもあるが、逐次、既存装置についてもできる改善を試みる。仮にすべてのムラを解消できなくとも、装置自体が持つ1次的なムラと、選別環境等がもたらす2次的なムラの区別ができれば分離効率の低下要因が整理でき、部分的に改善できる可能性がある。「形状のバラつき」については、前回述べた廃プラスチックのジグ選別におけるサイズ・形状を統括する数値指標を、他の選別装置に拡張することで、各装置について適切な整粒条件を確立できる見込みである。「滞留時間」は、元より、系統的な実験データの蓄積があれば一定精度での把握は可能であるが、単位時間当たりの処理量と選別精度との関係であるため、普遍的な最適条件が存在する訳ではない。各装置の定常運転時の滞留時間における状態を元に、装置ユーザが求める最適条件を選択できるような関係性を整理していく予定である。
以上、選別の不確実性に基づく、選別の再現性や分離効率の改善、選別工程の自動制御を実現する筆者らの取り組みをまとめると、図6.3.1のようになる。人の経験によらない自動制御で、少なくとも第41回・図6.1.1の「実現可能な最大分離効率」を超える分離効率を安定的に実現したいと考えている。なお、ここで言う「自動制御」とは、供給する選別対象物に応じて、予めシステムに組み込まれた選別装置・選別システムの制御モードを、人が選択することを意味している。一方、選別工程の前段において、センサーやAI認識を有するソータ等で情報を蓄え、情報が紐づけされた粒子群をバルク選別工程(次工程)に送ることで、制御モード自体も装置が選択する「自律制御」に発展し得るものと考えている。
図6.3.1 筆者の研究開発に基づく、不確定要素の解消による自動制御化の展望