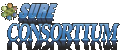第42回
バルク選別の不確実性 ②
~不確実性の改善余地~
不確実性の改善余地
前回は、「バルク選別の不確実性」によって分離効率の低下をもたらす、5つの主な要因ついてまとめた。これらを改善するには、各要因がどのような原因でもたらされているかを理解する必要がある。ここでは、不確実性をもたらす各要素の原因と改善の余地について考察してみる。
①「単体分離」については、筆者も長年、その認識の重要性については語ってきたが、実のところ、「単体分離を実現する方法」は元より、「単体分離の状態を精度よく分析する方法」もあまり進歩していない。現在、筆者らは、リサイクル向けに特化して、両者の技術を少しでも進歩させるための検討を続けているところである。特に前者で難しいのは、リサイクルでは対象となる廃製品の構造が、年々変化していくことである。対象物が長年変わらなければ、偶発的に上手くいく方法を発見することも期待できるが、リサイクル用途で継続的に実現するには、単体分離促進に関する普遍的な概念を構築しなければならない。現状の知見で実施するなら、例えば、1製品ずつ丁寧に解体すれば単体分離は実現するが、量産性が低下し、コストが増大する。小型家電のようなものを、1製品ずつ、単素材になるまで解体するのは合理的でないので、どこまで解体操作をするかを吟味することが重要である。また、その後の破砕による単体分離も、破砕機の制御には限界があるので、まとめて破砕しても単体分離性を損なわない対象物は何かを認知しなければならない。試行錯誤により一時的改善は期待できるが、長期にわたる安定した単体分離の実現は難しく、筆者らの検討で解釈に前進があれば、あらためて述べたいと思う。
②「ヘテロ凝集」については、一般にリサイクル工場で選別される数cm以上の粒子についてはほぼ発現することはなく、考慮しなくて良い。ただ、今後、より細粒の選別を実施した場合には、分離効率改善の盲点となる可能性がある。「ヘテロ凝集」の把握の難しさは、「その場観察(in situ analysis)」でないと確認できないことである。「単体分離」の分析は、通常、多数の粒子を樹脂内に埋め込み、表面を研磨してSEM-EDXなどを利用した分析装置で行う。一方、「ヘテロ凝集」では、選別装置内の空間において粒子が凝集(緩く結合)しているだけなので、分析のために他の環境に移したり、力を加えてしまうと凝集が解消されてしまう可能性がある。透明な媒体中に粒子が均一に分布していれば、濁度のような分析で凝集自体の把握はできるが、それがヘテロ凝集か、ホモ凝集(同種粒子の凝集)かは区別できない。実際の選別において、乾式法では湿度や水分によってその影響を受けるので、水分のコントロールが簡単な解決法となる。一方、湿式選別では、凝集を防ぐために分散剤を投入したり、超音波を照射したりするが、これによって本当にヘテロ凝集が解消されたかを確認する術がない。残念ながら、現時点では、起きていないことを祈るだけとなる。
③「選別装置の場のムラ」は、装置によって事情が異なる。磁選機などは、元々「場のムラ」による分離効率低下の影響が小さく、また、磁束密度分布から磁気力がどのように発現しているかを知ることができ、「場のムラ」の大きな装置、小さな装置を予め認識できる。筆者が過去に検討した気流選別機(比重選別)では、管内の上昇気流により軽産物を吹上げ、重産物を落下させて選別するが、通常、管内は中央部の気流速度が速く、周辺部は遅くなるので、風速のムラが分離効率低下をもたらす。筆者は、微弱な旋回流を発現させ、管内の断面風速を均一にする装置を開発したが、このように「場のムラ」の原因が明確であり、かつ、比較的簡単に解消できる例は多くない。
④「形状のバラつき」については、現状は、篩でなるべく粒度を揃えて選別するのが、正攻法である。形状自体のバラつきを抑えることはできないが、そもそも、どのような形状が分離効率の低下をもたらすかは選別装置によって異なり、必ずしも明確になっていない。筆者は、近年、廃プラスチックのジグ選別(比重選別)において、サイズ・形状を統括する数値指標を考案し、これを一定範囲に収めたサイズ・形状グループごとに事前整粒することで、分離効率の改善に成功した。現在、これを他の選別装置に応用する検討を進めており、概念がまとまったら紹介したいと思う。
⑤「滞留時間」については、各装置の特性を実験的に求め、このデータに基づいて適正な「滞留時間」を設定することはできる。ただし、選別対象が変動する場合は、特定のサンプルを検証するだけでは実用に向かない。第39回で述べたように、対象物の組成の変化やその分布などに応じて系統的な実験を行い、組成変動に対応し得るデータの蓄積が必要となる。
以上、これらはいずれも現状の課題であり、今後の研究開発要素であるが、今すぐできる対応をまとめると図6.2.1のようになる。
図6.2.1 不確定要素による分離効率低下の改善ー現状における対応の難易-