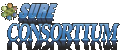第40回
選別工程導入の考え方 ⑤
~他産業における選別とは異なる点~
他産業における選別とは異なる点
前回のコラムの冒頭で、選別は様々な産業で用いられるが、リサイクルにおける選別では事情が異なることに触れた。15年程前のレアメタル高騰期、レアメタルリサイクルの選別装置開発を競っていた時期があった。多くは異分野からの新規参入であったが、筆者らは以前からこの課題に取り組んでいたため、既存技術では困難なこと、その達成には課題の克服が必要なことを当然の事実として認識していた。しかし、課題を克服した装置を展示会等でデモをすると、competitorと思われる新規参入者から、「こんな選別なら我が社の技術で簡単にできる」等のお声を多くいただいた。つまり、凄そうに見えない…というのである。筆者は「そんなことはない」と確信していたが、なぜそう思うのかが理解できなかった。その後、様々な業界の考えを理解するうち、当時の彼らの誤解がようやく理解できるようになった。その個別の要素は、これまでのコラムでも触れてきたが、ここでは、その要点をまとめてみる。
多くの農工業の生産現場で利用される破砕・選別に投入される原料は、通常、厳密に管理されている(図5.5.1 農工業製品の生産プロセス)。例えば、成分既知のAと、製造工程で混入した成分既知の異物Bを選別する操作などである。混入した異物は、Aと無関係な成分なので単体分離もされている。成分既知なので、どの選別物性を利用すれば効果的に選別できるかも既知であり、言わば、第32回で示した図4.2.1のA、B粒子条件1か2に該当する。リサイクル選別から見れば、極めて易しい対象物である。もちろんその分、高度な選別精度が求められるが、その高度さは選別自体の高度さではなく、対象物の選別容易さに裏打ちされたものである。一方、鉱山(図5.5.1 鉱山における選鉱プロセス)になると、元々ひと塊の石を砕くので、単体分離が影響する。しかし、サンプリング分析による採掘計画などに基づき、およそどういう組成の物が選別対象となるかは既知である。前記の農工業用途よりは選別の難易度が上がるため、それほど高度な選別はできず、異物除去の仕上げは製錬工程に任せることになる。これに対して、リサイクルで対象となる廃製品(図5.5.1 リサイクルにおける物理選別プロセス)は、これまでも述べてきたように、ロットごとの組成変動や経年変化も大きく、通常、入荷物の組成などは分析しない。前回のコラムで、分からないなりにグループ化してサンプリング分析することをお薦めしたが、他産業におけるサンプリング精度には遠く及ばない。個々の対象物の単体分離も組成も不明なまま破砕・選別を行うので、旧来、多くの素材は天然資源と同等の素材(製錬)原料にはならず、カスケードリサイクルを余儀なくされてきた。これを、製錬原料化して水平リサイクルを実現するという飛躍的な技術革新を実現するのが、次世代の選別技術に課せられた期待となる。
図5.5.1 各産業における選別プロセスの役割の違い
冒頭で示した展示会におけるデモでは、選別対象物は予測不可能なほど変動することを前提に代表的な模擬試料を用いたが、容易だと指摘した新規参入者は、毎回必ず成分既知の試料が投入されると誤解したのだろう。ただ、それにしても、現状の技術の組み合わせでは到底、実現不可能であった。破砕・選別装置のうち、リサイクル用途の市場は、現状、それほど大きくはないため、他産業で培われてきた装置をリサイクル向けに転用していることが多い。特に破砕機や集合選別機はそのほとんどが転用品であり、そもそもリサイクル向けに作られた装置ではない。一般論ではあるが、リサイクル向け導入の経験に乏しい、新規参入者の言う「優れた装置」には、実用的な見落としがあることが多い。選別技術は、その技術差を端的に、あるいは論理的に示しにくく、対象物に応じた選別困難さを多面的・総合的に解釈をしないと、正しく理解することができない。本コラムは、これらを構成する個別要素の判断基準を提供するものであり、読者の皆さんには、是非、その技術差を見抜くスキルを身に着けていただくことを期待する。