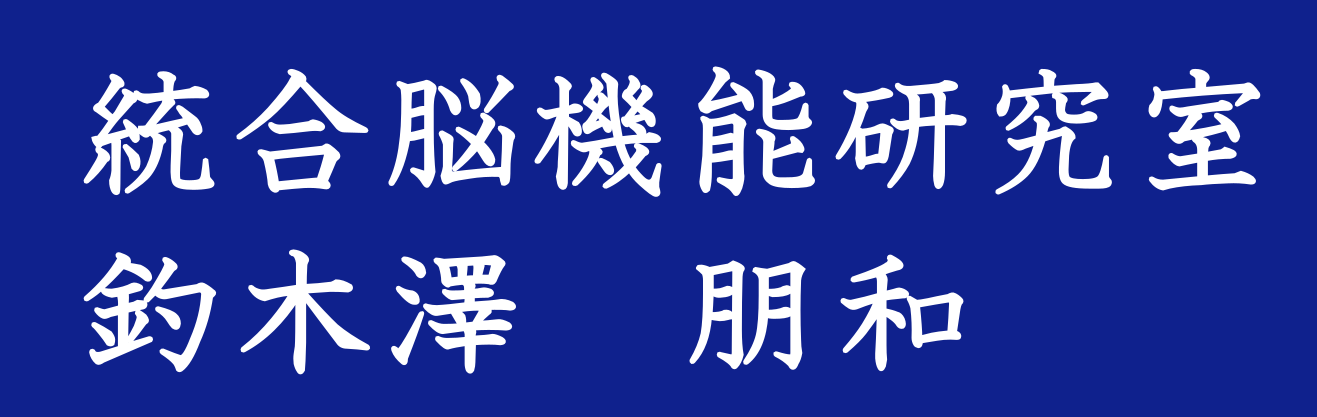産業技術総合研究所・筑波大学連携大学院統合脳機能研究室
脳の機能を統合的に理解するため、MRIによるマルチモーダル計測法の開発を行っています。筑波大学連携大学院理工情報生命学術院 システム情報工学研究群 知能機能システム学位プログラム (IMIS)准教授として大学院生の指導も行っており、希望する学生は技術研修生またはリサーチアシスタント(RA)として産総研で研究に従事することが可能です。内容については「研究紹介」、「研究業績」をご覧下さい。
お知らせ
- 2024/08/16募集中
- 大学院生募集中!!
筑波大学大学院システム情報工学研究群知能機能システム学位プログラム 連携大学院准教授として修士・博士課程の大学院生を募集しています。特に前臨床MRIを使ったげっ歯類研究に興味がある方は是非ご連絡ください。大学院のページ - 2025/02/25論文
- 大内さん(M2)の論文がFrontiers in Neuroanatomyにアクセプトされました。おめでとうございます!機能的・解剖学的ネットワークが年齢によりどのように変化するかを解析ました。
- 2025/02/17お知らせ
- 大内さん(M2)の修士論文がプログラムリーダー賞に選出されました!おめでとうございます。博士課程も引き続き精進して下さい。
- 2025/01/15論文
- 今村さん(D2)の論文がNeuroImageに掲載されました。おめでとうございます!従来のfMRI法ではげっ歯類の扁桃体(感情に重要な役割を担う領域)の撮像は困難でした。本論文で開発したzero-echo time imaging法はfMRI計測が可能でしかも偏桃体も撮像できます。今後の神経科学研究の重要なツールとして期待されます。
- 2025/01/15お知らせ
- ケベック大学博士1年佐竹さんが奨学給付金(Concours de bourses d'excellence départementales)を獲得しました。おめでとうございます!
- 2025/01/06お知らせ
- ヒト脳マッピング学会でシンポジウム講演と座長を務めます。
- 2025/01/06お知らせ
- 産総研に9.4T 前臨床MRIが導入されました!臨床用3T MRIと合わせてトランスレーショナル研究の加速が期待されます。大学院生、ポスドク、契約職員を募集しています。げっ歯類MRIを中心とした神経科学研究に興味のある方はまずは見学からお問い合わせください。
- 2024/08/16論文
- 大内さん(M2)の論文がNeuroImageに掲載されました。おめでとうございます!人間とマカクサルで脳の神経線維分布がどの領域でどの程度異なるのかを拡散強調画像法と機械学習を用いて明らかにした意欲的な論文です。マカクサル用RFコイルの作成から始めようやく第一報を掲載することができました。
- 2024/08/16お知らせ
- 第52回磁気共鳴医学会大会で教育講演「前臨床MRI」の座長を務めます。前臨床MRIの魅力と最新のトピックを紹介しますので興味のある方はご参加ください。
- 2024/08/09お知らせ
- 第28回NMRマイクロイメージング研究会でラボの学生たち(大内、今村、横田)がポスター発表を行いました。私は片栗粉を使ったex vivo micro-MRIの発表をしました。学生たちには普段触れることのないMRIのマニアックな世界を感じられたと思います。つくば発祥の研究会で私も世話人としてこれからも盛り上げていきたいです。
- 2024/08/01お知らせ
- Neuro2024で学生たち(大内、今村、佐竹)が発表を行いました。佐竹さんはカナダからの参加です。
- 2024/07/14論文
- Prof. Li, Prof. Cauliとの共同研究の論文がeLifeに掲載されました。第一著者のPhamさんが博士課程3年次にJSPSサマープログラムで来日した時の研究成果が含まれています。拡散強調画像による脳組織内の水分子拡散が、アストロサイトの活動と関連する脳内の水の移動度を示していることを示しました。
- 2024/07/01お知らせ
- MRI基礎講座の担当を務めています。MRIの初歩的な知識は持っているがさらに基礎を勉強したい人にお勧めです。
- 2024/05/10お知らせ
- ISMRM 2024で大内さんがポスター発表を行いました。初の海外発表です。
- 2024/04/24お知らせ
- 昨年まで私のラボでRAをされていた佐竹さんが5月から正式にUQTRの大学院博士課程で学位を目指します。おめでとうございます。UQTR Piche教授と私のdual supervisor制度を利用したプロジェクトです。これまでの研究に対する姿勢から素晴らしい成果を期待しています!
- 2024/04/03論文
- 佐竹さん(M2)の論文がFrontiers in Nutritionに掲載されました。かつおだしを飲んだ時に増強される脳の機能的結合を解明しました。Functional connectivityをだし摂取後の脳内の情報処理に応用した初の論文です。おめでとうございます!
- 2024/04/01お知らせ
- Université du Québec à Trois Rivièresの客員教授に就任しました。認知トレーニングの脳科学的効果に関する共同研究を開始します。日本から留学生も受け入れているので興味のある方はご一報ください。
- 2024/03/04論文
- 佐竹さん(M2)の論文がFrontiers in Neuroscienceに掲載されました。ワーキングメモリ―タスクの1つであるn-back task遂行時の正答率と相関のある脳の機能・構造を網羅的に解析しましました。おめでとうございます!
- 2023/09/19お知らせ
- 日本磁気共鳴医学会で教育講演の座長と講演を行います。トランスレーショナルMRIについて生理研の福永先生とともに議論を深めます。興味ある方は是非。
- 2023/09/15論文
- iScienceに手の運動中の脳の機能的結合の変化に関する論文を掲載しました。利き手と非利き手で機能的結合の変化が異なることを明らかにしました。
- 2023/07/05お知らせ
- 日本神経科学会(Neuroscience 2023)で国際シンポジウムを開催します。"Magnetic resonance- 物理と神経科学の共鳴、そして病態科学へ"と題して神経科学研究へのMRIの可能性について議論できればと思っています。
- 2023/05/27お知らせ
- 日仏生物学会で最優秀発表賞(Prix de la Meilleure Présentation Orale)を受賞しました(釣木澤)。
- 2023/05/09お知らせ
- ヒューマニクス学位プログラム3年 今村 彩子さんがISMRM2023 Trainee Stipend を受賞しました。おめでとうございます!
- 2023/05/09お知らせ
- ISMRM2023 Bruker Workshopで講演します。片栗粉とグリンパティックシステムに関する研究成果もポスター発表します。