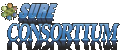第35回
選別機の運転条件 ④
~選別装置分類の整理(実態と運用)~
選別装置分類の整理(実態と運用)
これまで、「選別装置の選択」「選別機の運転条件」の各回において、様々な名称で装置の分類を提示してきた。これらはすべて、筆者のこれまでの経験に基づいて、各装置の機構をなるべく単純に整理した独自の分類である。従来のテキストにはこのような分類は記載されておらず、特にバルク性質利用の集合選別については分類が分かりにくく、各分類の関係についていささか混乱されているかもしれない。そこで今回は、これらの分類の整理を行う。
図4.2.4は、集合選別機における絶対運動/相対運動、境界条件確定型/後決め型の分類と、個別装置の位置づけを整理したものである。それぞれ、長年にわたり独自に発展してきた装置を、その機能に従って、筆者が後から分類したものであるので、中間的な性質に分類されるものも存在する。
図4.2.4 代表的なバルク性質利用集合選別機(乾式/湿式)の選別機構分類
まず、境界条件確定型の選別機は、基本的には絶対運動選別機となる。吊り下げ磁選機や気流選別機(カラム内で均一な風速を発生させる装置。風速にバラつきのある風力選別とは区別しているが、図中の分類としては同じカテゴリとなる)は、装置自体の設定条件が、粒子群選別の境界条件を決める。ドラム磁選機や渦電流選別機は、基本的に磁性/非磁性、導体/不導体を選別するもので、この基本性能を利用する上では、境界条件確定型となる。また、相対運動選別機であるジグは、機構的には境界条件を後決めができるが、通常、不特定多数の粒子を対象とすることはなく、フィードの重/軽粒子の比率が大きく変化しないことが前提である。このため、基本的には、状況に応じて境界条件を後で決められる構造になっていない。装置機構(原理)上は、境界条件後決め型といえるが、実態としては、ほぼ境界条件確定型として運用される。
一方、境界条件後決め型は、明確に磁着か非磁着かに分かれるような吊り下げ磁選機などとは異なり、粒子の選別物性に応じて運動に分布が生じるケースである。相対運動選別機であるエアテーブルが典型的な例と言えるが、粒子間の相互作用が選別にほとんど影響しない(絶対運動選別機である)湿式テーブルも、粒子運動に分布が発生じるため後決め型となる。また、ドラム磁選機や渦電流選別機も、上述したような通常の使い方では確定型であるが、飛翔距離に応じて、非磁性体を更にわずかな磁性の差で分けたり、導体を更にわずかな導電性の差で分けるなども、装置の構造上は可能である。通常、この方法では良好な選別は期待できないが、そのような利用をした場合には、飛距離に応じた回収対象は後で決められるので、境界条件後決め型要素も含まれることになる。
それぞれのタイプにどういう特徴があるかは、過去のコラムを参照いただければと思うが、各装置の特徴を把握し、これを最適に運転・運用する上で、ぜひ、この分類を理解していただきたい。