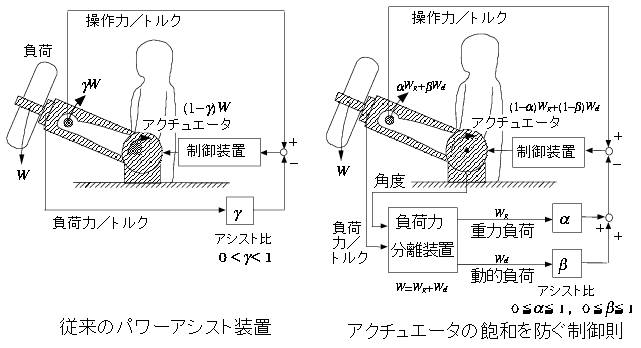
本研究では,健常ではあるが体力の衰えている高齢者,障害者あるいは病院等における介助者の機能/作業支援を目的とするパワーアシスト装置を開発する.すなわち,手軽に装備でき,かつ装着者の意志に応じて動作して,装着者の関節にかかる力学的負担を軽減することができる装置を開発するための機構/制御技術を確立し,高齢者の生活支援/福祉に貢献することを目的とする.
パワーアシスト系を設計する際の技術的課題の一つは,アクチュエータの飽和を回避し,アシスト比の均一性をいかに保持するかである.パワーアシスト系では,操縦桿と操縦されるアームが分離された通常の遠隔操作マニピュレータシステムと異なり,それらが一体化しているために,アームに作用する負荷が直接マスタにも加わる.そのためアームを駆動するアクチュエータが飽和した場合,アシスト比を減少させたのと等価な効果を生み,操作性を低下させるのみならず,安全性の観点からも問題となる.
駆動負荷が操作中一定の条件下では,このアクチュエータの飽和は,アシスト比を仕様値から減少させるものの,一定値を維持するため操作性への影響は少ない.しかし,例えば慣性負荷が含まれる場合は,操作中に負荷が変動するため,結果的にアシスト比も変動し,操作性や制御系の安全性が損なわれる一因となる.パワーアシストの従来の研究のほとんどは,アクチュエータが無限のトルクを出し得ることを前提に議論が進められている.発生トルクに限界を持つアクチュエータを用いて構成される実用パワーアシストシステムを開発する上では,アクチュエータ出力の非線形性にも配慮した制御システムの検討が必要である.
こうした現状認識に基づき,本研究室では,発生トルクが有限であるアクチェエータで構成される外骨格型パワーアシスト装置の制御システムに関する基礎的問題である,アクチュエータのトルク飽和がその操作性に及ぼす影響や,トルク飽和を回避するパワーアシストシステムの構成法の検討を進めている.その一環として,静的負荷(重力)と動的負荷を分離して,それぞれに異なるアシスト比を設定するシステムを研究している.
一般に人がある負荷を搬送する場合,物体の重力に依存する負荷は,人の挙動に関わらず常に作用する.したがって,操作者がアシスト装置を介してそれを保持するために必要とされる操作力は,人の最大負荷保持能力以下になるようにしなければならない.一方,操作者に作用する負荷の慣性力や粘性力は操作加速度や操作速度に依存して決まる.この性質は操作者が動作を調節することで,意識的に負荷負担の調整が可能なことをも意味している.そこで,有限の最大力・トルクを有するアクチュエータの能力を効率的に利用すべく,負荷を重力負荷と動的負荷に分離し,それぞれにアシスト比を設定するとともに,操作者の挙動に依存しない重力負荷のアシストを優先的に行うことで,トルク飽和を回避するという手法を提案した.
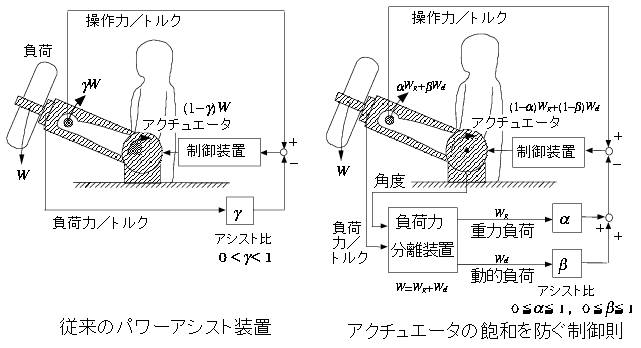
|
上記のアイデアに墓づき,電動産業用ロボットを用いて,3次元のパワーアシスト装置を試作した.このシステムでは,ロボットアームの先端に負荷がアームに作用する力・トルクを検知する6軸力・トルクセンサと,操作用ハンドルを介してアームに伝わる操作者の操作力を検知する6軸力・トルクセンサが設置されている. 今回試作したシステムは,産業用ロボットを利用して構築したものであり,ハードウェアそのものは,比較的大がかりなものである.将来的には,家庭内で手軽に使用できるコンパクトなシステムを開発することを目指している.
|
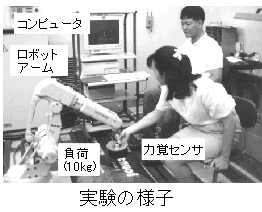
|