背景
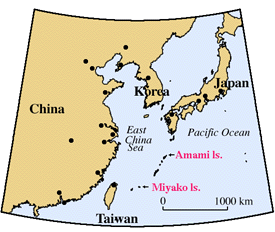 鹿児島県の奄美諸島および沖縄県の南西諸島は、東シナ海を取り囲む形で連なっている。
一方、右の地図中に●で示される主要都市は、大陸上ではそのほとんどが東シナ海に面する形で
存在していることから、この地域は大陸上から流れ出す汚染物質の主たる通路であるとい
える。したがって、大陸上から北太平洋地域への汚染物質の流れ出しの季節的変化を捉え
るうえで、これらの島嶼は定点観測地点としてきわめて有利な場所に存在することがわか
る。そこで、筆者は奄美大島、宮古島、西表島において1992年7月から1994年8月にかけて
粒径2μm以下の大気エアロゾルの捕集を1ヶ月平均で実施した。
鹿児島県の奄美諸島および沖縄県の南西諸島は、東シナ海を取り囲む形で連なっている。
一方、右の地図中に●で示される主要都市は、大陸上ではそのほとんどが東シナ海に面する形で
存在していることから、この地域は大陸上から流れ出す汚染物質の主たる通路であるとい
える。したがって、大陸上から北太平洋地域への汚染物質の流れ出しの季節的変化を捉え
るうえで、これらの島嶼は定点観測地点としてきわめて有利な場所に存在することがわか
る。そこで、筆者は奄美大島、宮古島、西表島において1992年7月から1994年8月にかけて
粒径2μm以下の大気エアロゾルの捕集を1ヶ月平均で実施した。nss.SO42-およびblack carbon濃度の季節変化
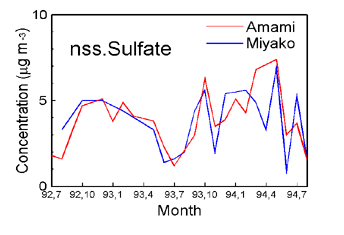 右図に奄美大島および宮古島でのnss.SO42-濃度の季節変化を
示す。両地点は直線距離で約600km離れているにもかかわらず、濃度および季節変化が
きわめて近いことがわかり、両地点でのnss.SO42-濃度はlocalというより
regionalな要因に支配されていることがわかる。また、nss.SO42-
は7月には1.5μg m
右図に奄美大島および宮古島でのnss.SO42-濃度の季節変化を
示す。両地点は直線距離で約600km離れているにもかかわらず、濃度および季節変化が
きわめて近いことがわかり、両地点でのnss.SO42-濃度はlocalというより
regionalな要因に支配されていることがわかる。また、nss.SO42-
は7月には1.5μg mまた、宮古島におけるnss.SO42-およびblack carbon (BC)濃度の 季節変化を右図(下)に示す。 BCの濃度はnss.SO42-より一桁低いが、その季節変化は同期して いることから、観測されたnss.SO42-の多くは 燃焼起源であることがわかる。BCの濃度レベルとしては、日本の大都市域での典型的な 測定値と比べて1/10から1/5程度の値である。
重金属成分濃度の季節変化
 重金属のうちMn、Ni、Asなど多くの成分は、右図に示されるように
nss.SO42-と同様の季節変化を示すが、ZnおよびPbには、
春期や秋期にnss.SO42-の増加を
大きく上まわる急激な濃度上昇を示すことがある。また、大陸から海上に長距離輸送された大気エアロゾルの測定例として、北アメリカより北大西洋のBermuda島へのnss.SO4
2-とVの輸送(Chen and Duce,1983)がよく知られているが、奄美および宮古島ではnss.SO42-とVの濃度の対応は明確ではない。これは、中国におけるSの発生源のうち、重油燃焼の占める割合が低いことを反映していると考えられる。
重金属のうちMn、Ni、Asなど多くの成分は、右図に示されるように
nss.SO42-と同様の季節変化を示すが、ZnおよびPbには、
春期や秋期にnss.SO42-の増加を
大きく上まわる急激な濃度上昇を示すことがある。また、大陸から海上に長距離輸送された大気エアロゾルの測定例として、北アメリカより北大西洋のBermuda島へのnss.SO4
2-とVの輸送(Chen and Duce,1983)がよく知られているが、奄美および宮古島ではnss.SO42-とVの濃度の対応は明確ではない。これは、中国におけるSの発生源のうち、重油燃焼の占める割合が低いことを反映していると考えられる。多環芳香族炭化水素(PAH)成分濃度の季節変化
 多環芳香族炭化水素(Polycyclic Aromatic Hydorcarbons, PAHs)は、その強い変異源性
注目される物質であり、ディーゼル車排気中の粒子に含まれることで知られる。また、
石炭、重油などの化石燃料の燃焼からも排出されることが知られており、人為汚染の長
距離輸送の指標となる可能性も指摘されている。
多環芳香族炭化水素(Polycyclic Aromatic Hydorcarbons, PAHs)は、その強い変異源性
注目される物質であり、ディーゼル車排気中の粒子に含まれることで知られる。また、
石炭、重油などの化石燃料の燃焼からも排出されることが知られており、人為汚染の長
距離輸送の指標となる可能性も指摘されている。奄美・宮古で捕集された大気エアロゾル中のPAHs 個々の物質の濃度は、どれも冬季に極大を 迎えるが、いくつかのPAHsの濃度比を検討してみると、新たな情報が得られる可能性がある。 B[a]P と B[e]Pの排出源での濃度比は約 1であるが、B[a]Pの方が大気中での光分解速度の方が 速いことが知られている。したがって、B[a]P / B[e]Pの比が低い場合、そのエアロゾルは 排出後、大気中に長時間浮いていた、言い換えれば滞在時間が長い(long lived)ものであると 考えることができる。
 また、Flu / Pyr比は発生源での燃焼時の温度に依存する。この比が高い比の場合、固定
発生源の寄与が低い、すなわち自動車排気を起源とする粒子の寄与が高いと解釈すること
ができる。右図に、宮古島における、B[a]P / B[e]PおよびFlu / Pyrの季節変化を示す。
これより、たとえば1994年5月の宮古島におるPb, Znの急増は、相対的に滞留時間短いエ
アロゾル(近距離から輸送された)によるものであると推測され、一方、真冬のnss.SO4
2-等の汚染物質は相対的に長時間滞留した(長距離輸送された)もので
あることがわかる。
また、Flu / Pyr比は発生源での燃焼時の温度に依存する。この比が高い比の場合、固定
発生源の寄与が低い、すなわち自動車排気を起源とする粒子の寄与が高いと解釈すること
ができる。右図に、宮古島における、B[a]P / B[e]PおよびFlu / Pyrの季節変化を示す。
これより、たとえば1994年5月の宮古島におるPb, Znの急増は、相対的に滞留時間短いエ
アロゾル(近距離から輸送された)によるものであると推測され、一方、真冬のnss.SO4
2-等の汚染物質は相対的に長時間滞留した(長距離輸送された)もので
あることがわかる。